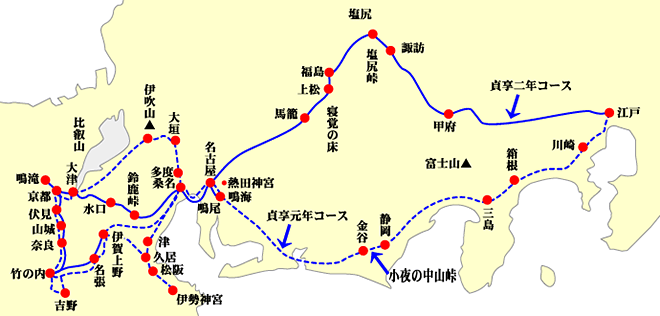旅と句
野ざらし紀行(43句)
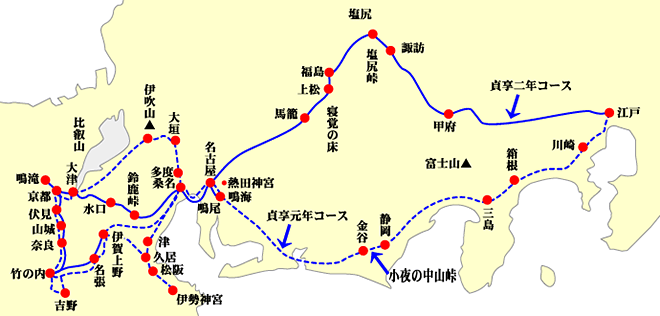
貞享元年(1684)8月〜貞享2年4月末 芭蕉41歳
貞享元年(1684)8月、芭蕉は門人千里を伴い、初めての文学的な旅に出る。東海道を上り、伊勢山田・伊賀上野へ。千里と別れて大和・美濃大垣・名古屋・伊賀上野へ帰郷し越年。奈良・京都・大津・名古屋を訪ね、江戸へ帰るまでの9か月にも及ぶ旅。「野ざらし」を心に決意しての旅であっただけに収穫も多く、尾張連衆と巻いた『冬の日』は風狂精神を基調として、新風の萌芽がみられる。
紀行文の名称は、『草枕』『芭蕉翁道の記』『甲子吟行』など多数みられるが、今日では『野ざらし紀行』が広く用いられている。「漢詩文調」からの脱却と蕉風樹立の第一歩となる。芭蕉自筆の画巻や元禄11年(1689)刊の『泊船集』などの刊本の形で伝わっている。
野ざらしを心に風のしむ身哉
秋十とせ却て江戸を指古郷
霧しぐれ富士をみぬ日ぞ面白
猿を聞人捨子に秋の風いかに
道のべの木槿は馬にくはれけり
馬に寝て残夢月遠し茶のけぶり
三十日月なし千年の杉を抱あらし
芋洗ふ女西行ならば歌よまむ
蘭の香やてふの翅にたき物す
蔦植て竹四五本のあらし哉
手にとらば消ん涙ぞあつき秋の霜
わた弓や琵琶になぐさむ竹のおく
僧朝顔幾死かへる法の松
碪打て我にきかせよや坊が妻
露とくとく試みに浮世すゝがばや
御廟年経て忍は何をしのぶ草
義朝の心に似たり秋の風
秋風や藪も畠も不破の関
死にもせぬ旅寝の果よ秋の暮
冬牡丹千鳥よ雪のほととぎす
明けぼのや白魚白きこと一寸
しのぶさへ枯て餅買ふやどり哉
狂句木枯の身は竹斎に似たる哉
草枕犬も時雨るかよるのこゑ
市人よ此笠うらう雪の傘
馬をさへながむる雪の朝哉
海暮れて鴨の声ほのかに白し
年暮ぬ笠きて草鞋はきながら
誰が聟ぞ歯朶に餅おふうしの年
春なれや名もなき山の薄霞
水とりや氷の僧の沓の音
梅白し昨日や鶴を盗れし
樫の木の花にかまはぬ姿かな
我がきぬに伏見の桃の雫せよ
山路来て何やらゆかしすみれ草
辛崎の松は花より朧にて
命二つの中に生たる桜哉
いざともに穂麦喰はん草枕
梅恋ひて卯花拝む涙哉
白げしにはねもぐ蝶の形見哉
牡丹蘂ふかく分出る蜂の名残哉
行駒の麦に慰むやどり哉
夏衣いまだ虱をとりつくさず